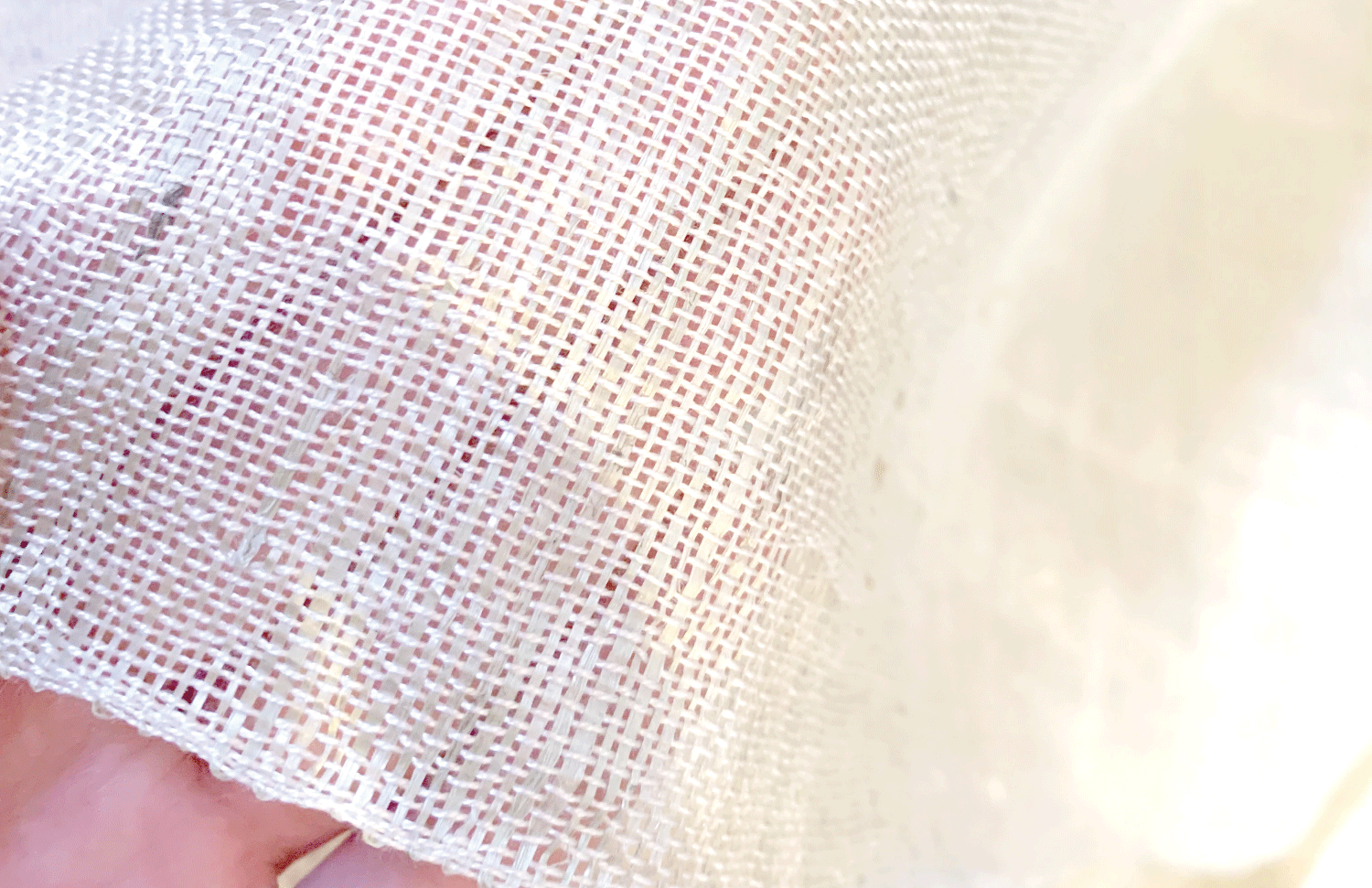2023年8月葛布作りワークショップに参加しました。
猪名川葛布ワークショップに参加しました。
8月7日・11日に、葛布作りを学びに葛布のワークショップを行なわれている兵庫県川西市の辻さんのご自宅へ、「猪名川葛布つくりワークショップ」に参加してきました。
私自身葛布に触れるのは2回目で、前回は掛川市に葛の本の撮影でお邪魔したときに、葛のつるの採取・煮る・川洗い・織り作業を簡単に体験させていただいたことがあります。その際も大変だと感じたのですがやはり記憶も朧気になってしまっていたため、改めて気を引き締めて今回の葛布作りワークショップに参加させていただきました。
葛布とは
葛布とは、その名の通り「葛」で作った布のことで、葛のつるから靭皮繊維をとりだし糸にし、それを紡いだ織物です。
基本的に糸とは繊維を引き伸ばして撚りをかけたものになりますが、静岡県遠州地方の葛布は、緯(よこ)糸に使う葛糸に撚りをかけず、平糸で綺麗な光沢がみえるよう織るところに特徴があるのだそうです。
葛布は中国、周代(紀元前1046~紀元前256年)には衣服として存在していたと考えられ、日本でも古墳時代前期の古墳で最古の葛布が出土しています。しな布・芭蕉布とともに日本三大原始布の一つに数えられており、万葉集や延喜式・平家物語にも登場し、その美しさや乾きやすさ、軽さから平安貴族の装束や、武士の袴下にも用いられてきました。
明治維新後、武士の消滅、生活の変化、資材の不足等、様々な要因から葛布の生産・需要は大幅に少なくなったものの、葛糸独特の光沢や艶、手触り、通気性の良さや丈夫さから、現在においても本場である静岡県掛川市を中心にバックや財布、服飾品や壁紙など多種多様に使われており、その伝統を継承するために様々な施策に取り組まれています。
【1日目】葛の刈り取りと発酵
1日目は葛のつるをとるところからはじめました。
良い葛糸を作るためには様々なポイントがあります。
①つるを切った時に白い芯がないこと ②まっすぐ太く綺麗なものをとること ③2mくらいのものをあつめること、などなど。
一本一本葛のつるを切って中身を確かめていくのですが、そう簡単には白い芯がないものはみつかってくれません。色々なところに引っかかっている葛のつるを引っ張るのも体力がいりますし、一本の葛のつるを何回か切ってやっと白い芯がなくなったと思ったら長さが50cmくらいになってしまったものも何本かありました。良さげな場所も辻さんや他参加者さまはすぐに見つけてらして、葛の根もそうですが経験と見極める力が必要な作業だと感じました。
白い芯がないものをみつけた時の嬉しさはぜひ一度味わっていただきたいです!
夏にぴったりな美味しいフルーツや羊羹をいただき体力が回復したところで、5~10本ほど切ったつるを集め、鍋に入れやすいように円状に巻いた後麻ひもで所々くくっていきます。その後、辻さん宅へもどり、沸騰した大鍋で先ほどの葛のつるの束を120分ほど煮ていきました。

煮ている間は葛布についての歴史や海外でも使われている事などをお教えいただき、たくさんの素敵な葛布で作ったものも見せていただきました。
平織の美しい光沢がこれから糸を作っていくワクワク感を増してくれます。
またお昼には鹿肉が入ったキーマカレーもいただき、しっかり元気をつけさせていただきました。
ときおり上下返しながら120分煮ていると葛のつるの色が段々変化していきます。
刈った時は少しくすんだ緑だったのが火が通り鮮やかな緑色に、そして同じくマメ科である枝豆のような香りも感じました。
じっくり煮て色が抜けて薄黄緑のつるになったところで、つるの表面を触ってみます。
ぬるっとした感触があり柔らかくなっていたらしっかり煮れているということで、すぐに水につけて冷まします。
そしていよいよ発酵の工程へ、葛のつるの発酵に必要なススキの室で発酵を行なっていきます。
ススキに含まれる「枯草菌」がつるを発酵させてくれ、皮をはがしやすく中の繊維を取りやすくしてくれます。
辻さん宅でお教えいただいた室作りの方法は2つ。
ブルーシートとお鍋を使った室作りの方法です。
ブルーシートは敷いた上にススキ→葛束→ススキ→ブルーシートで覆ったもの。
もっと簡易的にやるならば大鍋にススキを少量ひいて葛束→ススキ→フタといった方法をお教えいただきました。
季節にもよりますがだいたい3~5日ほど発酵させていきます。
毎日発酵状況を確かめ、葛の表面がぬるぬる・そして枯草菌の白い菌糸ができていることが確認できたらきちんと発酵ができている合図です。
1日目は室に入れたところで終了だったため、毎日の発酵具合は辻さんにみていただきました。
【2日目】川での葛洗いとツグリ作り
2回目のワークショップ時には発酵ができた状態のもので「洗い」の工程を体験させていただきました。
前回作った葛のつるの束にはしっかりと白の菌糸ができています。
天気や気温によっても発酵具合が変わるため、毎日発酵状況を確かめることが大切だとお教えいただきました。
丁度ふくらはぎくらいが濡れるくらいの美しい川をみつけてくださり、そこで発酵したつるを洗います。川は夏にはちょうど良く程よい冷たさがあり、とても気持ちが良かったです。
くくっていた麻紐をほどいたら熊出の持ち手ににつるをひっかけ、川の流れにそって「くそかわ(葛についている薄い表皮)」を手でなでるように取っていきます。
そこから芯をしごき靭皮繊維をはがしていくのですがなかなかうまくはがれず・・・
強く抑えず力を抜きながらはがしたらうまくいきやすいと教えていただき、何度目かでスッとはがすことが出来ました。
うまくはがれたときはすごくスッキリします。
全てはがすことができたら、繊維についている黒の斑点やワタをある程度取って川にさらしておきます。この時も優しく丁寧に扱わないと細かく裂けてしまうためより集中しながら行いました。
しばらく晒していると、刈り取ったつるからは想像できない綺麗な白っぽいベージュの繊維が川の中でゆらゆらと動き、太陽の光にあてられキラッと艶めきます。その様子がすごく穏やか綺麗で自然の美しさを感じました。
くそかわやワタを食べに小さな魚が集まってくるのもとてもかわいく癒されました。
ある程度川でさらしたら川から取り出し、草の上で乾かしていきます。乾かし終えたものは葛苧(くずお)と呼ばれます。
乾かしている間は辻さんが作ってくださったサンドイッチをいただきながら、自然の中で贅沢な時間を過ごさせていただきました。
また辻さん宅へもどり、葛苧を乾かしている間、先日いただいた葛の糸でツグリ作りを行ないました。
葛の糸はあらかじめ2mmに裂いて「葛布結び」という方法で結んでいきます。そうして1本の糸にしていく作業を績む(うむ)というのですが、それがまた集中力が必要な作業です。
通常の糸のように強い糸ではなく、少し力を入れて引っ張るだけでちぎれてしまう繊細な糸なので、一本一本を結ぶだけでもかなり大変です。切れ目をいれたところが2mmで丁度良いと思っても、自然の物なので割いていく途中でちぎれたり細くなったり・・・
またその細い糸を結んでいく作業でも少し力を入れて引っ張ってしまえばどんなに長く2mmにできたとしても簡単にちぎれてしまいます。学生の頃家庭科で使った糸とはまったく違い、これでハンカチを作ろうものなら一体何日かかるのだろうと、改めて天然の素材の繊細さに大変さに驚くのと同時に本当に終わるのかと何度か心も折れました。
ツルをとったところから体験させていただき、その時点でも糸を作る大変さを感じていたので、何とか結びたい、ある程度形にしたいという思いでなんとかある程度まで結び終える事が出来ました。すべてを結べた時の感動・達成感はひとしおです。
やっとの思いで績みあげた糸でいよいよツグリを作っていきました。
ただそこで私が績んだ糸には問題がありました。
それは結び目の向き。
実際に作った糸を塗り箸に巻き付けツグリを作っていくのですが、結び目が左右バラバラになると織る際に使うシャトルの穴から糸が出てこず、ひっかかってちぎれてしまいます。私の糸は一部がそうなってしまっていたため、結ぶの一つにしても意味があることを改めて身にしみて感じました。
向きを直せたら箸に指をおいて八の字に巻いていきます。箸を持った左手をうまく動かして糸を撒いていく事で効率よく巻きやすくなるのですが、またここでも細すぎる糸を使うと簡単にちぎれてしまいます。
本当にひとつひとつに理由があって工程を作られている事を感じました。
つぐりの状態になったもの・川で洗ったものは持って帰り、次のワークショップでコースターにして完成になります。
実際に作られたコースターなどもみせていただいたのですが、平織だからこそ分かる葛布独特の艶や光沢が本当にキレイで自然のもの、しかも葛でこんな素敵なものができあがることが楽しみになりました。

当たり前のようにある布のはじまりの一つに、今日作った葛布のような自然の糸があること、化学繊維では出せない独特の艶や輝きがあること
実際に自分で体験してみないと分からない大変さや嬉しさがあることが分かりました。
自分の服を繊維の部分までまじまじとみつめたことはなかったのですが、改めて自分の服を見た時に
何本の糸で作られているのか考えさせられ、様々な技術の上で安心安全に着れている事、
大事にしなければならないとこの強く感じる二日間となりました。
次回は自分で一からつくった葛糸で実際にコースターを作ってきます。
また報告しますので楽しみにしていてください!